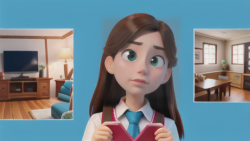設計
設計 家の重さを支える力:垂直力
家は、常に重力の影響を受けています。この重力によって上から下へかかる力を、垂直力と呼びます。 家の重さ自体も垂直力の一つで、これは固定荷重と呼ばれます。壁や床、屋根など、家を作っている材料の重さは変わりませんので、固定荷重は常に一定です。
固定荷重以外にも、家には様々な垂直力がかかります。例えば、家具や電化製品、そこに住む人たちの重さ。これらは積載荷重と呼ばれ、生活の中で変化します。家族が増えたり、大きな家具を新しく買ったりすれば、積載荷重は増えますし、逆に引っ越しなどで荷物が減れば、積載荷重は減ります。このように積載荷重は、住む人の生活スタイルによって変動するのです。
また、場所や季節によっても垂直力は変化します。 冬に雪が屋根に積もれば、その重さが家にかかります。これは積雪荷重と呼ばれ、雪の量によって大きさが変わります。雪がたくさん積もる地域では、この積雪荷重に耐えられるように家を建てる必要があります。積雪荷重を考慮せずに家を建てると、屋根が壊れてしまう恐れがあります。
さらに、地震の揺れも垂直方向の力を発生させます。地震の揺れは、地面を上下に揺らし、その力は建物にも伝わります。地震による垂直力は、家の重さに加えて大きな負担となり、建物を壊してしまうこともあります。
このように、家には様々な垂直力がかかっています。固定荷重、積載荷重、積雪荷重、そして地震による力。これらの力をしっかりと考慮して家を建てることが、安全で快適な暮らしを送るためにとても大切なのです。