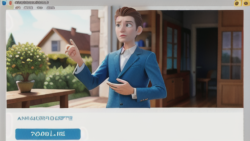設計
設計 デッドスペースを有効活用!
家は、家族みんなが心地よく暮らすための大切な場所です。しかし、限られた面積の中で、いかに空間を有効に使うかは、住まいの快適さを大きく左右する重要な課題です。
特に、設計上どうしてもできてしまう「使われていない空間」を、どう活用するかが鍵となります。このような空間は、階段の下や屋根裏部屋の傾斜した天井部分、あるいは柱や梁が出っ張っている部分など、家の中の様々な場所に存在します。一見すると無駄な空間にも思えますが、アイデア次第で貴重な収納場所になったり、個性的な場所を演出するアクセントになったりする、隠れた可能性を秘めているのです。
例えば、階段下の空間は、ちょうど良い高さの棚を設置することで、本や雑貨、季節物の家電などを収納するのに最適な場所に変わります。奥行きがある場合は、引き出し式の収納棚にすれば、デッドスペースを余すことなく活用できます。また、屋根裏部屋の傾斜した天井部分は、低い家具を配置することで、書斎や趣味の部屋、子供の遊び場など、特別な空間に早変わりします。さらに、梁の出っ張りを逆手に取って、観葉植物を飾ったり、間接照明を取り付けたりすることで、おしゃれな空間を演出することも可能です。
家の広さに関わらず、誰もが抱える「使われていない空間」問題。この問題を解決することができれば、限られた面積でも広々と感じられる、快適で機能的な住まいを実現できるでしょう。収納場所を増やすだけでなく、空間を有効活用することで、日々の暮らしがより豊かで快適なものになるはずです。