織部板:床の間の粋な演出

リフォームの初心者
先生、『織部板』って床の間にある板のことですよね?どんな板かよくわからないのですが、教えていただけますか?

リフォーム専門家
そうだね。『織部板』は床の間の正面上部に、だいたい幅24cmくらいの柾目の板のことだよ。床の間の廻り縁(天井と壁の境目にある縁)の下についていることが多いね。

リフォームの初心者
幅24cmくらいなんですね。掛け軸とかを掛ける板とは違うんですか?

リフォーム専門家
そうだね、掛け軸を掛ける場所とは違うよ。掛け軸は床の間に立てるのが一般的だね。『織部板』には、花を生けた花器や香炉などを飾ったり、掛け物を飾ったりすることもあるけれど、何も飾らず、板だけの床の間もあるんだよ。
織部板とは。
床の間の正面上部に、幅およそ24センチほどのまっすぐな木目の板が取り付けられていることがあります。この板は「織部板」と呼ばれています。掛け軸などを掛けるために釘を打つこともありますが、床の間には必ずしもこの板があるとは限りません。位置としては、床の間の上部の、廻り縁と呼ばれる縁の下あたりに設置されます。
織部板とは

織部板とは、床の間の上部に水平に設置される、幅の狭い板のことを指します。多くの場合、幅は約二十四センチほどの柾目板が用いられます。柾目板とは、木の年輪に対して垂直に切り出した板のことで、反りや狂いが少ないという特徴があります。この織部板は、床の間の正面、廻り縁と呼ばれる縁取りの装飾材のすぐ下に取り付けられます。
茶室や和室といった、日本の伝統的な様式の部屋において、床の間は、掛け軸や花を生けるなど、その部屋の中でも特に重要な場所です。そして、この織部板は、床の間の格式を高め、荘厳な雰囲気を醸し出す上で重要な役割を担っています。
織部板という名前の由来は、安土桃山時代の茶人として名高い、古田織部が好んで用いたことに由来すると言われています。古田織部は、自由な発想と型破りなデザインで知られ、茶道具や建築にもその個性を遺憾なく発揮しました。織部焼と呼ばれる、独特の風合いを持つ焼き物も、彼の代表作として広く知られています。
織部板もまた、古田織部の美意識を反映したものであり、飾り気のない簡素さの中にも、確かな存在感を放つ佇まいが特徴です。床の間に飾られる掛け軸や花、そして、床の間そのものの雰囲気と調和しながら、織部板の素材や色合いは慎重に選ばれます。木材の種類や木目、そして、漆塗りや着色といった仕上げ方によって、様々な表情を見せる織部板は、床の間の雰囲気を大きく左右する重要な要素と言えるでしょう。茶道の精神である侘び寂びの世界観を、より一層深く感じさせるための、静かで奥深い魅力を秘めた存在、それが織部板です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 名称 | 織部板 |
| 設置場所 | 床の間の上部(廻り縁の下) |
| 形状 | 幅の狭い水平な板(約24cm) |
| 材質 | 柾目板(木の年輪に対して垂直に切り出した板) |
| 特徴 | 反りや狂いが少ない |
| 役割 | 床の間の格式を高め、荘厳な雰囲気を醸し出す |
| 由来 | 古田織部が好んで用いたことに由来 |
| 美意識 | 飾り気のない簡素さの中にも、確かな存在感 |
| その他 | 木材の種類、木目、仕上げ方(漆塗り、着色など)によって様々な表情を見せる |
織部板の役割

織部板は、床の間に設置される板のことです。飾り付けの役割だけでなく、実用的な機能も兼ね備えています。まず、掛け軸や生け花、香炉などを飾る際に、紐を掛けて固定する場所として使われます。季節の移ろいに合わせて、お正月には門松の掛け軸、春には桜の絵、夏には涼しげな風鈴、秋には紅葉の掛け軸、冬には雪景色を描いた掛け軸など、様々な飾り物を掛けることで、床の間全体の雰囲気を彩り、季節感を演出することができます。
織部板には、小さな釘を打って、掛け物を吊るすための紐を固定することもあります。これにより、掛け物が安定し、風で揺れたり、落下したりするのを防ぎます。また、織部板自体が美しい木目や漆塗りで仕上げられている場合もあり、それ自体が床の間の装飾としての役割を果たすこともあります。
しかし、すべての床の間に織部板が設置されているわけではありません。床の間の様式や、家の持ち主の考え方によって、設置されない場合もあります。例えば、茶室などでは、簡素な美しさを追求する「侘び寂び」の精神に基づき、あえて織部板を設置しない床の間も存在します。そのような床の間は、飾り気のない簡素な空間でありながら、静寂と落ち着きを感じさせ、見る人の心を和ませます。
織部板の有無にかかわらず、床の間は日本の伝統的な住まいにおいて大切な場所です。日常の喧騒から離れ、静かに自分と向き合うための空間として、あるいは、客をもてなすための特別な場所として、大切に扱われています。織部板は、そのような床の間の機能性と美しさを高める、さりげないながらも重要な役割を担っていると言えるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 織部板 |
| 設置場所 | 床の間 |
| 役割 | 飾り付け、実用機能 |
| 機能 | 掛け軸、生け花、香炉などを飾る際の紐を掛ける場所。 釘を打って掛け物を吊るし、安定させる。 板自体が装飾となる場合もある。 |
| 装飾例 | 正月:門松、春:桜の絵、夏:風鈴、秋:紅葉、冬:雪景色 |
| 設置の有無 | 床の間の様式や家の持ち主の考え方による。茶室などでは設置しない場合もある。 |
| 設置しない場合の考え方 | 侘び寂び |
| 床の間の役割 | 日常から離れ、自分と向き合う空間、客をもてなす特別な場所 |
織部板の素材と種類

織部板とは、床の間に飾られる長押の上にある横長の板のことです。 掛軸や花入れを飾る背景となるため、床の間の雰囲気を大きく左右する重要な要素となっています。古くから、織部板には主に杉や檜といった木材が使われてきました。これらの木材は、美しい木目と心地よい香りが特徴です。また、湿気に強く、腐りににくいという性質も持っています。そのため、長く使い続けることができ、大切に扱えば何世代にもわたって受け継ぐことも可能です。
杉は、全体的に赤みを帯びた柔らかな色合いをしています。木目は比較的まっすぐで、落ち着いた印象を与えます。一方、檜は、白っぽい明るい色合いで、清々しい雰囲気を醸し出します。木目は杉に比べてやや複雑で、独特の風合いがあります。このように、木材の種類によって色合いや風合いが異なるため、床の間の雰囲気や好みに合わせて選ぶことができます。
近年では、伝統的な木材以外にも、竹や和紙といった様々な素材で織部板が作られるようになってきました。竹は、軽くてしなやかでありながら、強度も高い素材です。竹の織部板は、すっきりとした見た目で、現代的な空間に馴染みます。和紙は、繊細で柔らかな風合いが魅力です。和紙を幾重にも重ねて作られた織部板は、独特の温かみと奥行きを感じさせます。
素材だけでなく、デザインも多様化しています。従来のシンプルなデザインに加え、彫刻や蒔絵を施した豪華なものや、幾何学模様などの現代的なデザインを取り入れたものも登場しています。伝統的な様式を尊重しつつ、現代の住宅にも調和するデザインが求められています。
織部板を選ぶ際には、床の間の広さや、飾る掛軸や花入れとのバランスも考慮することが大切です。素材やデザインだけでなく、大きさや厚みも様々な種類があります。部屋全体の雰囲気との調和も考えて、じっくりと時間をかけて選ぶことで、より一層床の間の美しさを引き立てることができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 床の間に飾られる長押の上にある横長の板。掛軸や花入れを飾る背景。 |
| 材質(伝統的) |
|
| 材質(現代的) |
|
| デザイン |
|
| 選択時の注意点 | 床の間の広さ、掛軸・花入れとのバランス、大きさ、厚み、部屋全体の雰囲気との調和 |
織部板の設置と注意点
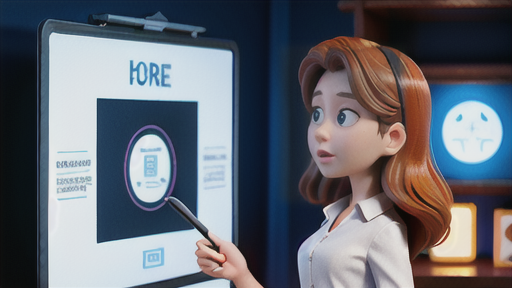
織部板は、その独特の緑色が床の間に静寂と落ち着きを与え、和室の雰囲気を格調高く演出する重要な役割を担います。設置にあたっては、全体の調和を損なわないよう、細心の注意が必要です。
まず、床の間の寸法と織部板の大きさを正確に測り、最適な配置を検討します。廻り縁や床柱とのバランス、そして床の間全体の雰囲気との調和を考慮することが大切です。中心に据える場合でも、あえてずらして配置する場合でも、意図を持って設置することで、より洗練された空間を創り出すことができます。
設置工事は、専門の業者に依頼することを強くお勧めします。専門家は、豊富な経験と知識に基づき、美しく安全な設置を実現してくれます。下地の処理や釘の打ち方、固定方法など、一見些細な工程にも、職人の技術が光ります。仕上がりの美しさはもちろんのこと、地震など災害時の安全性も考慮した確かな施工は、専門家ならではと言えるでしょう。
もしも、ご自身で設置に挑戦される場合は、安全に十分配慮し、慎重な作業を心掛けてください。釘を打つ際は、下地材にしっかりと固定されているか確認し、必要に応じて補強材を追加するなど、安定性を確保することが重要です。また、作業前に取扱説明書をよく読み、手順を理解しておくことも欠かせません。
設置後も、定期的なお手入れで美しさを保つことが大切です。織部板の素材によっては、乾燥によってひび割れが生じることがあります。木材の場合、年に数回、乾拭きで埃を落とし、専用のオイルや蜜蝋などを塗布することで、乾燥を防ぎ、艶を保つことができます。また、直射日光や湿気を避けることも、劣化を防ぐ上で重要なポイントです。こまめな手入れと適切な環境管理によって、織部板の美しさを長く楽しむことができるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 和室の床の間に静寂と落ち着きを与え、格調高い雰囲気を演出する |
| 設置時の注意点 | 床の間の寸法と織部板の大きさを正確に測り、廻り縁や床柱とのバランス、全体の雰囲気との調和を考慮して最適な配置を検討する |
| 設置工事 | 専門業者への依頼を推奨(下地の処理、釘の打ち方、固定方法など、専門知識と技術が必要) |
| 自身で設置する場合 | 安全に配慮し、取扱説明書をよく読んで手順を理解、釘打ち時の下地確認、必要に応じた補強材の追加、安定性の確保 |
| 設置後のお手入れ | 定期的な乾拭き、専用オイルや蜜蝋の塗布、直射日光や湿気を避ける |
織部板のある暮らし

織部焼の板を床の間に用いると、そこは日本の伝統美が息づく特別な場所になります。 床の間は、元々家の格式を示す場として、また客をもてなす際に心を伝える大切な場所として使われてきました。そこに、深い緑と釉薬の景色が美しい織部焼の板を据えることで、一層趣深い空間が生まれます。
季節の移ろいを彩る花や、書画を巻いた掛け軸を飾れば、自然と一体となる日本の美意識がそこに現れます。 春には桜や桃の枝、夏には涼しげな朝顔、秋には紅葉した枝もの、冬には椿や南天など、その時々の草花を飾ることで、部屋の中にいながらにして自然の美しさを感じ、心豊かに過ごすことができます。 また、茶の湯などの客をもてなす席では、織部板のある床の間が、亭主の心遣いと美意識を伝える場として重要な役割を果たします。 客人は、床の間に飾られた花や掛け軸を眺めながら、亭主のもてなしの心に触れ、共に豊かな時間を過ごすことができるでしょう。
現代の暮らしの中でも、織部焼の板を和室や居間に用いることで、落ち着いた雰囲気を作り出すことができます。 和風の空間だけでなく、現代的な空間にも意外なほど調和し、独特の存在感を放ちます。 織部焼の板は、単なる飾りではなく、日本の文化や心を伝える大切なものと言えるでしょう。その深い緑色は、自然の力強さを表し、不均一な釉薬の景色は、わびさびの精神を伝えます。
織部焼の板のある暮らしは、私たちの心にゆとりと豊かさを与えてくれるでしょう。 慌ただしい日常の中で、ふと床の間の織部板に目を向ける時、自然の美しさや日本の伝統文化に触れ、心静かなひとときを過ごすことができるはずです。それは、現代社会を生きる私たちにとって、かけがえのない心の安らぎとなるでしょう。
| 要素 | 詳細 |
|---|---|
| 織部焼の板の設置場所 | 床の間(和室、居間) |
| 床の間の役割 |
|
| 織部焼の板の効果 |
|
| 季節の飾り |
|
| 織部焼の特徴 |
|
