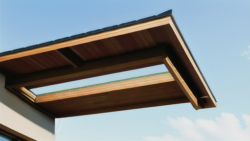水回り
水回り 知っておきたい貯水槽:シスターンタンク
私たちが生活する上で、水は欠かせません。朝起きて顔を洗い、ご飯を炊き、お風呂に入る。毎日、様々な場面で私たちは水を使っています。この大切な水を安定して使えるようにするのが貯水槽の役割です。
水道管から送られてくる水を一時的に貯めておくことで、もしもの断水時にも、一定期間は水を使うことができます。断水は、水道管の工事や災害など、様々な原因で起こります。そんな時でも、貯水槽があれば、すぐに水が止まってしまう心配はありません。トイレや手洗いなど、最低限の水を確保できるという安心感は、私たちの生活に大きなゆとりをもたらします。
貯水槽は水の供給を安定させるという役割も担っています。例えば、朝晩など、水の使用量が多い時間帯は、水道管の水圧が弱くなることがあります。このような時、貯水槽に貯めておいた水を使うことで、水圧の低下を防ぎ、安定した水量を確保することができます。蛇口をひねればいつでも安定した水量が出るというのは、快適な生活を送る上でとても重要なことです。
近年、地震や台風などの自然災害が増加しています。災害時に水道が止まってしまうと、生活に大きな支障が出ます。そのため、災害への備えとして貯水槽の重要性はますます高まっています。特に、多くの人が生活する集合住宅では、貯水槽は必要不可欠な設備と言えるでしょう。もしもの時に備えて、貯水槽の設置や点検をしっかりと行うことが大切です。
貯水槽は普段はあまり意識することがないかもしれませんが、私たちの生活を支える重要な設備です。安心して水を使える暮らしは、貯水槽によって守られていると言えるでしょう。