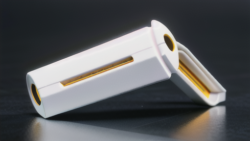健康住宅
健康住宅 化学物質過敏症と家のリフォーム
近頃は、住まいの模様替えをする際に、体の調子への影響を気にする人が増えてきました。特に、ある特定の化学物質に何度も触れているうちに、少しの量でも触れただけで頭痛やめまい、吐き気といった様々な症状が出てしまう「化学物質過敏症」への関心が高まっています。この症状は、人によって反応する物質や症状の重さ、続く期間などが大きく異なり、原因となる物質を特定することが難しい場合もあります。
住まいの模様替えは、新しい建材や塗料、接着剤などを使うため、化学物質に触れる機会が増える可能性があります。そのため、模様替えを計画する際は、化学物質過敏症についてよく理解し、症状が出るのを防ぐための工夫をすることが大切です。具体的には、揮発性有機化合物(VOC)の少ない建材を選ぶ、施工中の換気を十分に行う、完成後もしばらくは換気を続けるといった対策が有効です。
建材を選ぶ際には、VOCの放散量が少ないことを示す「F☆☆☆☆」表示のある製品を選ぶと良いでしょう。また、壁材には珪藻土や漆喰など、自然素材を用いるのも一つの方法です。珪藻土は湿気を調整する機能があり、漆喰は抗菌性や防カビ性に優れています。
施工中は窓を開け放つなどして、十分な換気を心掛けましょう。また、作業をする職人さんの健康にも配慮し、換気扇を設置したり、防塵マスクを着用してもらうなどの対策も必要です。模様替えが完了した後も、しばらくは換気を続けることで、残留する化学物質の濃度を下げることができます。
化学物質過敏症は、症状が重くなると日常生活に支障をきたす場合もあります。住まいの模様替えは、快適な暮らしを実現するためのものですが、健康を損ねてしまっては元も子もありません。事前の情報収集や適切な対策を講じることで、健康 risks を最小限に抑え、安心して模様替えを行いましょう。