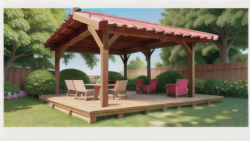素材
素材 便利な板材、パーティクルボード
木のくずを集めて板にしたもの、それが砕片板です。この板は、木を細かく砕いた木片を、接着剤で固めて作られています。のこぎりで木を切ったときに出るおがくずや、木材を必要な大きさに切ったときに出る余りの木などを活用しているので、木の資源を無駄なく使えることが大きな利点です。
砕片板を作る工程では、木片の向きをばらばらにすることで、板全体の強度が均一になります。そのため、板が反ったり割れたりしにくいという特徴も持っています。また、木を細かく砕いているので、大きな一枚板を作るのも簡単です。さらに、使う木の材料を選ばないので、他の板に比べて値段が安いことも魅力です。
砕片板は、そのまま使うこともできますが、表面に薄い化粧板を貼ったり、塗料を塗ったりすることで、見た目も美しく仕上げることができます。例えば、木目模様のシートを貼れば、まるで一枚板のように見せることも可能です。また、好きな色の塗料を塗れば、部屋の雰囲気に合わせた家具を作ることもできます。
加工のしやすさも砕片板の大きな特徴です。のこぎりや錐などで簡単に加工できるので、日曜大工にも向いています。棚や机など、自分の好きな形に加工して、オリジナルの家具を作ることができます。このように、砕片板は様々な用途に使える、便利な材料なのです。