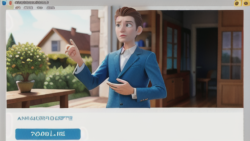工法
工法 小舞下地:日本の伝統工法
小舞下地とは、日本の伝統的な建築工法において、主に和室の壁を構築する際に用いられる下地材のことを指します。 小舞とは、細い竹や木を格子状に組んだもので、その上に土壁や漆喰を塗って仕上げることで、最終的に「小舞壁」と呼ばれる壁が完成します。
小舞下地を作る際には、まず柱と柱の間に水平に細い木を打ち付けます。これを「貫(ぬき)」と呼びます。次に、この貫に沿って、垂直に細い竹や木を並べていきます。これらを「小舞掻(こまいかき)」と呼びます。 そして、小舞掻を固定するために、小舞縄と呼ばれる専用の縄を用いて、格子状に編み込んでいきます。この作業は熟練した技術が必要とされ、縄の締め方や間隔によって、壁の強度や仕上がりの美しさが大きく左右されます。
小舞下地には、壁の強度を高めるだけでなく、独特の風合いを生み出すという役割もあります。格子状に組まれた小舞は、表面に凹凸を作り出し、土壁や漆喰がしっかりと付着するのを助けます。また、この凹凸によって、光と影の微妙な変化が生まれ、和室特有の落ち着いた雰囲気を醸し出します。
小舞下地は、日本の伝統的な建築技術の粋を集めたもので、高い耐久性と美しさを兼ね備えています。 しかし、近年では、施工できる職人が減少しており、貴重な技術となっています。そのため、小舞下地の技術を継承し、未来に残していくことが重要です。現代の建築においても、その優れた性能と風合いを生かし、新たな形で活用していく方法が模索されています。