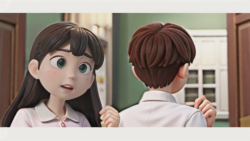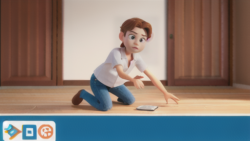工法
工法 転ばし床:リフォームの基礎知識
転ばし床とは、コンクリートの土間や地面などの上に、直接木を組んで床を作る工法のことを指します。土台となる横木(根太や大引)を土間の上に並べ、その上に床板を張るという、比較的シンプルな構造です。
一般的な床組みでは、地面と床の間に十分な空間を設けますが、転ばし床は床下の空間をほとんど作らないのが特徴です。そのため、床の高さをあまり高くすることができません。この特徴から、増築部分の床の高さを既存の建物に合わせたい場合や、天井が低い部屋で床下の空間を確保するのが難しい場合などに採用されることが多い工法です。
転ばし床のメリットは、工事が簡単で費用を抑えられる点にあります。複雑な工程が少なく、工期も短縮できるため、費用対効果が高いのが魅力です。
一方で、デメリットとして湿気が溜まりやすい点が挙げられます。床下の空間が狭いため、空気の流れが悪く、湿気がこもりやすくなります。この湿気が原因で、木材が腐ったり、シロアリが発生するリスクが高まります。特に、日本の高温多湿な気候では、湿気対策が非常に重要になります。
そのため、転ばし床を施工する際には、防湿シートや調湿材などを用いて、床下の湿気を防ぐ対策をしっかりと行う必要があります。地面からの湿気を遮断し、床下の換気を良くすることで、木材の腐朽やシロアリの発生を抑制し、建物の寿命を延ばすことに繋がります。また、定期的な点検やメンテナンスも忘れずに行い、建物の状態を良好に保つことが大切です。