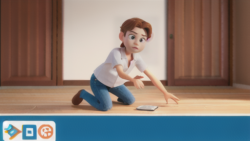法規
法規 二項道路:知っておくべき注意点
二項道路とは、法律で定められた幅が4メートルに満たない狭い道路のことを指します。正式な名前ではなく、建築基準法第四十二条第二項に規定されていることから、一般的に二項道路と呼ばれています。みなし道路と呼ばれることもあります。この二項道路に面して家を建てる場合は、特別な条件を満たさなければ建築許可が下りないため、注意が必要です。
二項道路は、特に都市部や古くからある住宅地でよく見られます。狭い道路に家が密集している地域では、火事が起きた際の延焼を防いだり、避難経路を確保したり、消防車や救急車などの緊急車両が通行できるように、建築基準法によって家の建築に制限が設けられています。
具体的には、二項道路に面した土地に家を建てる際には、道路の中心線から2メートル後退した位置に家を建てなければなりません。この後退した部分を道路として提供することで、実質的な道路幅を4メートル以上に確保することを目的としています。
この2メートル後退のルールは必ず守らなければならないわけではなく、地域によっては4メートルに満たない道路でも、すでに有効な道路幅員が確保されている場合があります。また、セットバックしてもなお道路幅員が確保できない場合もあります。そのような場合は、特定行政庁との協議が必要となり、建築基準法の規定に基づいて個別に判断されます。二項道路に面した土地に家を建てる際には、事前に自治体や専門家に相談し、必要な手続きを確認することが重要です。