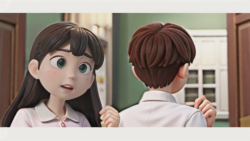工法
工法 杭打ちで家を支える:軟弱地盤対策
家は地面の上に建っています。これは誰もが知っている当たり前のことです。しかし、この地面、つまり地盤が、家の耐久性や安全性を大きく左右するということは、意外と知られていないかもしれません。
地盤が固くしっかりしていれば、家は安定して建ち、地震などの災害時にも倒壊のリスクが軽減されます。反対に、地盤が弱いと、家が傾いたり、壁にひび割れが生じたりする可能性があります。家が傾くと、ドアや窓の開閉がスムーズにいかなくなるだけでなく、雨漏りの原因にもなります。ひび割れも、見た目が悪いだけでなく、家の強度を低下させ、地震に対する耐久性を弱めてしまう恐れがあります。
特に注意が必要なのは、水分を多く含んだ軟弱地盤です。軟弱地盤は、建物の重さに耐えきれず、不均一に沈下する可能性があります。これを不同沈下と言います。不同沈下は、家の傾きを引き起こす大きな原因の一つです。また、地震の際には、軟弱地盤は揺れを増幅させるため、家がより大きなダメージを受ける危険性があります。
そのため、家を建てる際には、まず地盤の性質を詳しく調べる必要があります。地盤調査によって、地盤の強度や土質、地下水位などが分かります。もし軟弱地盤と判断された場合は、地盤改良工事などの適切な対策が必要です。地盤改良工事には、セメント系固化材を地盤に混ぜて固める工法や、杭を地中に打ち込んで建物を支える工法など、様々な方法があります。
家を建てるということは、家族が安心して暮らせる安全な場所を築くということです。地盤への配慮は、家の安全性を確保するための第一歩であり、快適な暮らしを守る上で欠かせない要素と言えるでしょう。